- 2025年8月15日
- 2025年10月2日
急な動悸が心配な方へ|脈管専門医が教える症状別の見分け方と受診のタイミング
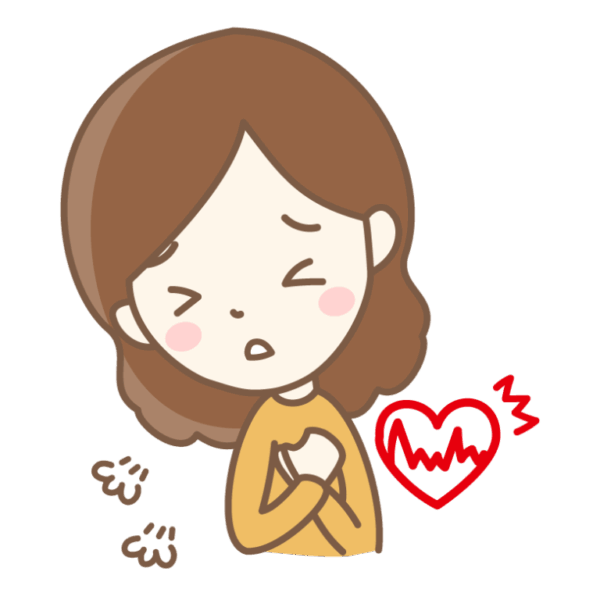
「ドキドキする」「心臓がバクバクする」「胸がドンドンと響く感じがする」といった動悸の症状を経験したことがある方は多いのではないでしょうか。動悸は日常生活でよく起こる症状の一つですが、その原因は実に様々です。
運動後や緊張した時の動悸は生理的なもので心配ありませんが、中には心疾患や他の病気が隠れている場合もあります。「この動悸は大丈夫なのかな」「病院に行った方がいいのかな」と不安に思う方も多いでしょう。
今回は、脈管専門医として動悸の原因や種類、そして適切な対処法について詳しく解説します。
この記事を読んでいただき、安心して日常生活を送るためのお手伝いができれば幸いです。

この記事を書いた、院長の高見 友也です。
『不安を安心に』変えることのできるクリニックを目指して、幅広い診療を行っています。ここでは、いくつかの専門医をもつ立場から、病気のことや治療のことをわかりやすく説明しています。
プロフィールはこちらから
🎥 この記事の内容を動画でご覧いただけます
お忙しい方や、まずはざっくり知りたい方のために、この記事のポイントを動画にまとめました。ぜひご覧ください。
ラジオ風の音声形式なので、家事や移動中など「ながら聞き」にもぴったりです。
目次
【動悸の種類と原因|心配な動悸と心配のない動悸の見分け方】

動悸とは、自分の心臓の鼓動を意識的に感じる状態のことです。通常、私たちは心臓の鼓動を意識することはありませんが、何らかの理由で心拍数が増えたり、心拍のリズムが乱れたりすると、動悸として感じられます。
動悸は大きく「生理的動悸」と「病的動悸」の2つに分けられます。
生理的動悸は健康な人にも起こる正常な反応で、運動時、興奮時、緊張時、発熱時などに起こります。これらは心配する必要のない動悸です。
一方、病的動悸は何らかの病気が原因で起こる動悸で、適切な治療が必要になる場合があります。心疾患、甲状腺機能亢進症、貧血、不安障害などが原因となることがあります。
動悸の感じ方も人それぞれです。「ドキドキする」という表現が最も一般的ですが、「バクバクする」「ドンドンと響く」「心臓が飛び跳ねる感じ」「心臓が止まりそうになる」など、様々な表現で訴える患者さんがいらっしゃいます。
心配な動悸の特徴として、安静時に突然起こる動悸、長時間続く動悸、胸痛や息切れを伴う動悸、失神しそうになる動悸などが挙げられます。これらの症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
逆に、運動後に起こり数分で治まる動悸、明らかな誘因(コーヒー、アルコール、ストレスなど)がある動悸、短時間で自然に治まる動悸などは、比較的心配の少ない動悸と考えられます。
不整脈による動悸も重要です。期外収縮(きがいしゅうしゅく)という軽い不整脈では、「心臓が一瞬止まる感じ」や「ドンと強く打つ感じ」を訴える方が多くいます。多くの場合は心配ありませんが、頻繁に起こる場合は検査が必要です。
【動悸を引き起こす主な病気|症状の特徴と危険度の判断】
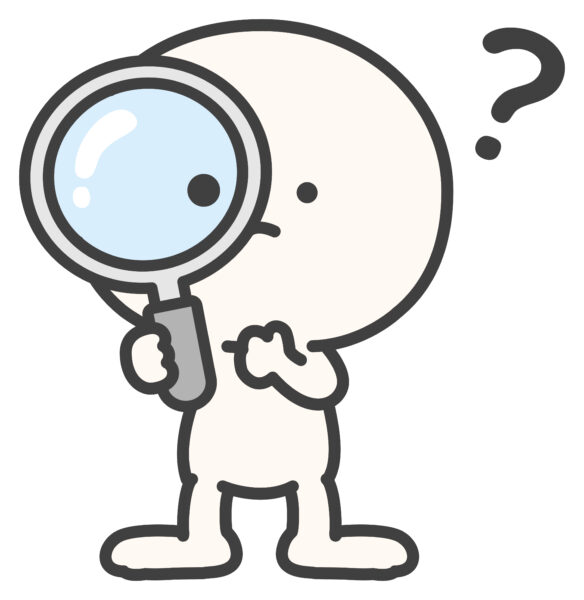
動悸を引き起こす心疾患として、最も注意が必要なのは不整脈です。不整脈には様々な種類があり、それぞれ症状や危険度が異なります。
心房細動(しんぼうさいどう)は、心房が細かく震えるような不整脈で、脈が不規則になります。「脈がバラバラで気持ち悪い」「心臓がバタバタする感じ」と表現される方が多いです。血栓ができやすくなり、脳梗塞のリスクが高まるため、適切な治療が必要です。
発作性上室頻拍(ほっさせいじょうしつひんぱく)は、突然心拍数が150回以上になる不整脈です。「急に心臓がバクバクし始めて止まらない」という症状が特徴的で、通常は突然始まって突然止まります。
心室頻拍や心室細動は生命に危険を及ぼす重篤な不整脈です。意識を失ったり、失神したりする場合があり、緊急の治療が必要になります。
心疾患以外の原因も多くあります。甲状腺機能亢進症(バセドウ病)では、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、常に動悸を感じるようになります。手の震え、体重減少、暑がりなどの症状も一緒に現れることが多いです。
貧血も動悸の重要な原因です。赤血球が少なくなると、心臓は酸素を全身に送るために働きを強めるため、動悸として感じられます。疲労感、めまい、息切れなどの症状も伴います。
更年期障害による動悸も女性に多く見られます。女性ホルモンの変化により自律神経が乱れ、動悸、ほてり、発汗などの症状が現れます。
パニック障害や不安障害では、強い不安感とともに動悸、発汗、息苦しさなどが突然現れます。「死んでしまうのではないか」という強い恐怖感を伴うことが特徴的です。
薬剤性の動悸もあります。気管支喘息の薬、風邪薬に含まれる成分、一部の抗うつ薬などが動悸を引き起こすことがあります。新しく薬を始めた後に動悸が出現した場合は、薬との関連を疑う必要があります。
【動悸の対処法と予防策|受診の目安と日常生活での注意点】
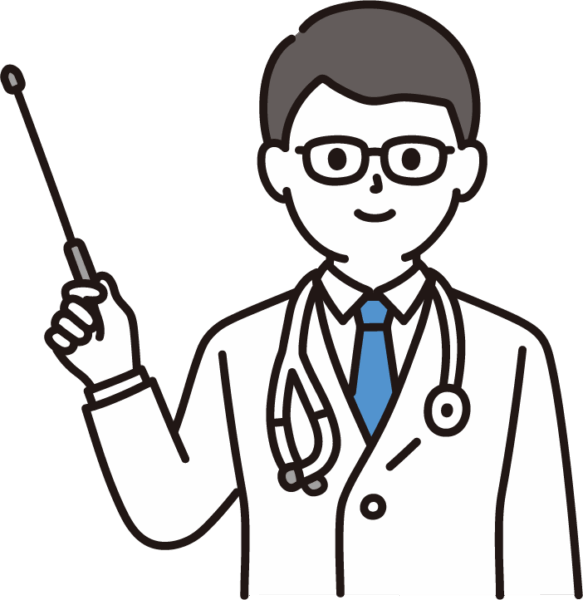
動悸が起こった時の対処法は、その原因や症状によって異なります。まず、安全な場所で安静にすることが基本です。座るか横になって、深呼吸をしながら症状が治まるのを待ちましょう。
発作性上室頻拍のような突然始まる動悸の場合、バルサルバ法という方法が効果的なことがあります。これは、鼻をつまんで口を閉じ、息を吐こうとする動作を10秒程度行う方法です。ただし、心疾患がある方は医師に相談してから行ってください。
ただし、以下のような症状がある場合は、すぐに救急車を呼ぶか医療機関を受診してください。胸痛を伴う激しい動悸、息切れが強い動悸、意識がもうろうとする動悸、冷や汗を伴う動悸などです。
日常生活での予防策も重要です。カフェインの摂取量を控えめにしましょう。コーヒー、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、動悸を誘発することがあります。1日のコーヒーは2杯程度に留めることをお勧めします。
アルコールも動悸の原因となることがあります。適量を守り、飲み過ぎないよう注意してください。また、喫煙は心血管系に悪影響を与えるため、禁煙することが大切です。
睡眠不足やストレスも動悸を引き起こしやすくします。規則正しい生活リズムを心がけ、十分な睡眠を取るようにしましょう。ストレス解消法として、軽い運動、読書、音楽鑑賞など、自分に合った方法を見つけることが重要です。
受診の目安として、週に数回以上動悸が起こる場合、動悸が5分以上続く場合、動悸とともに胸痛や息切れがある場合、日常生活に支障をきたす場合などは、医療機関を受診することをお勧めします。
受診時は、動悸の起こり方、持続時間、きっかけ、伴う症状などを詳しく医師に伝えてください。可能であれば、動悸が起こった日時や状況をメモに記録しておくと診断に役立ちます。
まとめ
動悸は多くの人が経験する一般的な症状ですが、その原因は様々です。多くの場合は心配のない生理的な反応ですが、中には治療が必要な病気が隠れている場合もあります。
重要なのは、動悸の性状や伴う症状をよく観察し、心配な特徴がある場合は早めに医療機関を受診することです。また、日常生活での予防策を実践することで、動悸の頻度を減らすことができます。
一人で不安を抱え込まず、気になることがあれば遠慮なく相談してください。適切な診断と治療により、動悸の不安から解放され、安心して日常生活を送ることができるでしょう。
あなたの心臓の健康を守るため、動悸に対する正しい知識を持ち、適切な対応を心がけていただければと思います。

気になった方やご心配な方、
お気軽にご相談ください。
ご予約は、こちらから。
