- 2025年9月17日
- 2025年9月29日
インフルエンザワクチンの効果と副作用|最新情報と接種のタイミング

毎年冬になると流行するインフルエンザ。
「ワクチンを打った方がいいの?」「副作用は大丈夫?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回、多くの患者さんと向き合ってきた経験から、インフルエンザワクチンについてお伝えします。

この記事を書いた、院長の高見 友也です。
『不安を安心に』変えることのできるクリニックを目指して、幅広い診療を行っています。ここでは、いくつかの専門医をもつ立場から、病気のことや治療のことをわかりやすく説明しています。
プロフィールはこちらから
🎥 この記事の内容を動画でご覧いただけます
お忙しい方や、まずはざっくり知りたい方のために、この記事のポイントを動画にまとめました。ぜひご覧ください。
ラジオ風の音声形式なので、家事や移動中など「ながら聞き」にもぴったりです。
目次
【インフルエンザワクチンの効果|本当に予防できるの?】
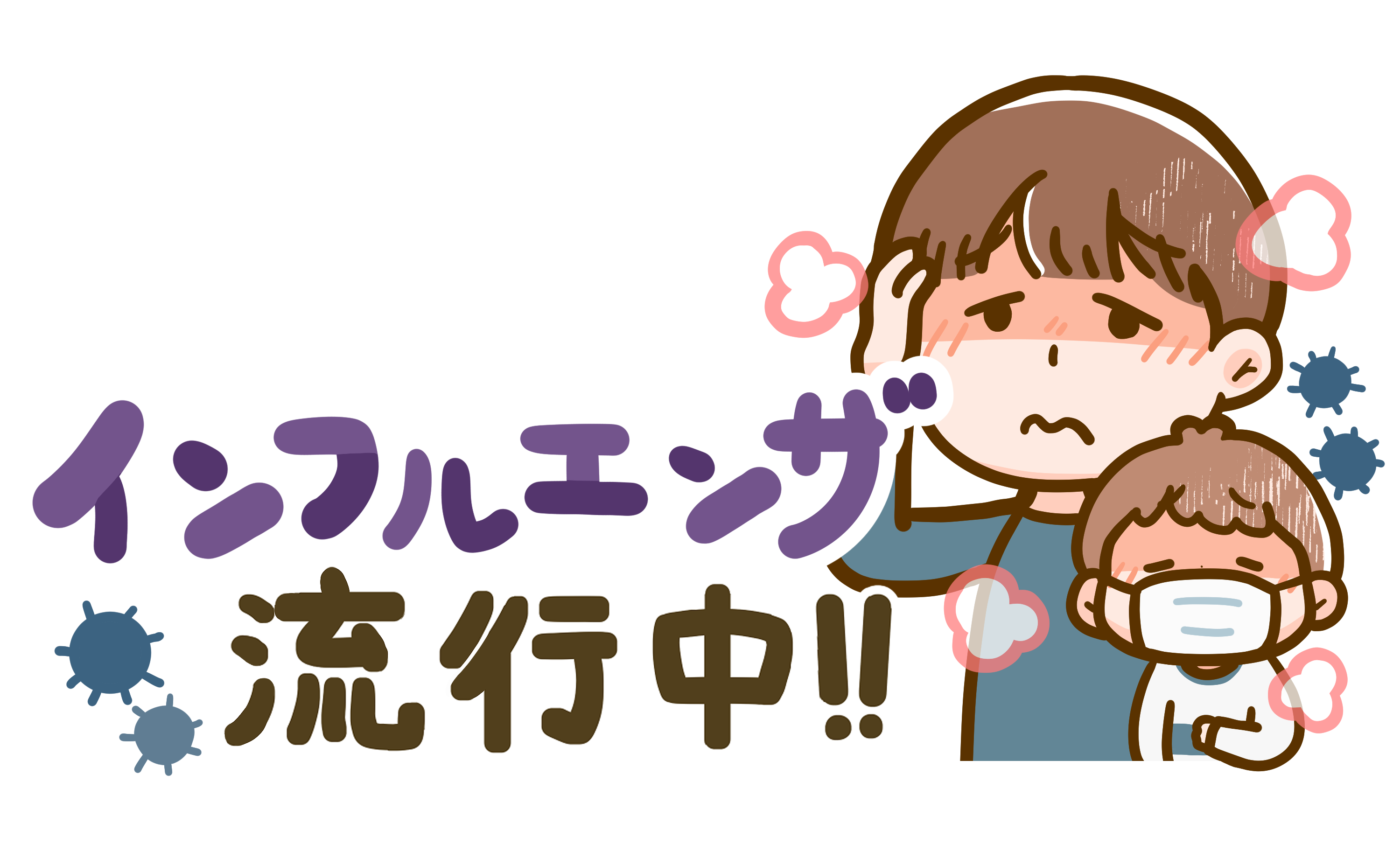
≪ワクチンの仕組みを分かりやすく説明≫
インフルエンザワクチンは、体の中に「インフルエンザウイルスの設計図」を送り込むようなものです。この設計図を見た免疫システム(体を守る仕組み)が、本物のウイルスが来た時に素早く対応できるように準備をしてくれます。
ワクチンに含まれているのは、毒性を弱めたり完全に無害にしたりしたウイルスの成分です。これによって病気になることなく、免疫を作ることができるのです。
≪実際の予防効果はどれくらい?≫
厚生労働省の発表によると、インフルエンザワクチンの有効率は約50~60%とされています。つまり、ワクチンを接種することで、半分以上の人がインフルエンザにかからずに済むということです。
「100%じゃないなら意味がないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、感染症予防において50~60%の効果は決して低くありません。さらに、たとえ感染してしまっても、症状が軽く済む効果も期待できます。
≪重症化予防効果が最も重要≫
ワクチンの最大のメリットは、重症化を防ぐことです。特に高齢者の方や持病のある方では、インフルエンザが肺炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあります。
ワクチンを接種することで、入院が必要になるリスクを約70%減らすことができるという研究結果もあります。これは非常に大きな効果といえるでしょう。
【副作用とリスク|安全性について知っておこう】
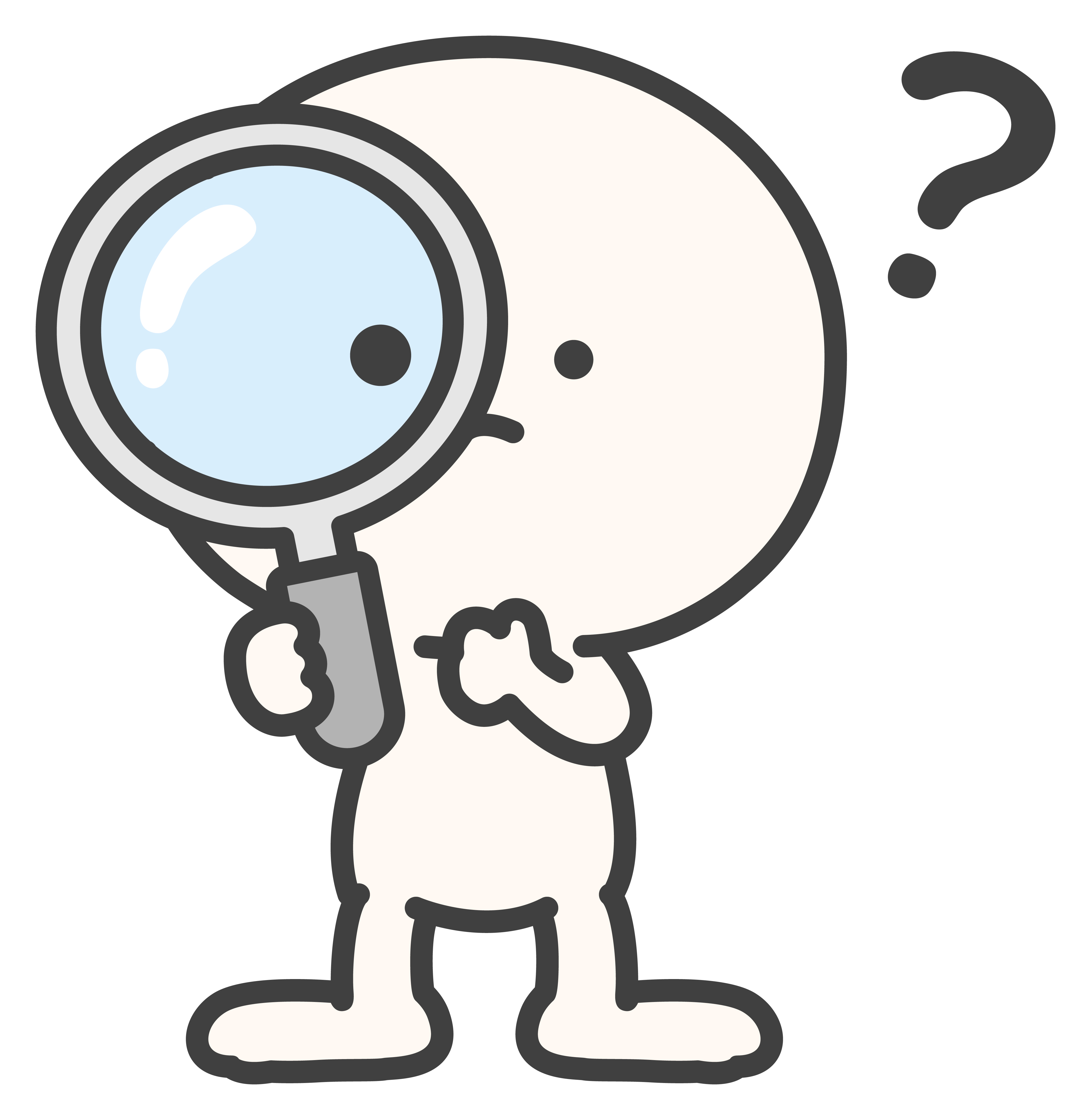
≪よくある副作用≫
多くの方が心配される副作用ですが、実際にはほとんどが軽微なものです。
最も多いのは接種部位の痛みや腫れで、約20%の方に見られます。
その他の症状として、軽い発熱、だるさ、頭痛などが起こることがありますが、これらは通常1~2日で自然に改善します。これは体が免疫を作っている証拠でもあるのです。
≪重篤な副作用の頻度≫
重篤な副作用として最も注意すべきは、アナフィラキシー(全身性のアレルギー反応)です。
しかし、その発生頻度は100万回接種あたり1.35回と極めて低いものです。
≪接種を避けるべき人・注意が必要な人≫
以下の方は接種を控える、または医師と相談が必要です。
発熱している方、重篤な急性疾患にかかっている方は、体調が回復してからの接種をお勧めします。
また、過去にワクチンでアナフィラキシーを起こした方は接種できません。
卵アレルギーのある方については、以前は接種を控えることが多かったのですが、現在では軽度のアレルギーであれば医師の管理下で接種可能とされています。
≪妊婦・授乳婦の接種について≫
妊婦さんや授乳中の女性にとっても、インフルエンザワクチンの接種は有益と考えられています。
妊娠中にインフルエンザにかかると重症化するリスクが高いため、積極的な接種が推奨されています。
また、妊娠中に接種することで、生まれてくる赤ちゃんにも免疫が移行し、生後6か月までの間、赤ちゃんをインフルエンザから守る効果も期待できます。
【接種時期とタイミング|いつ受けるのがベスト?】
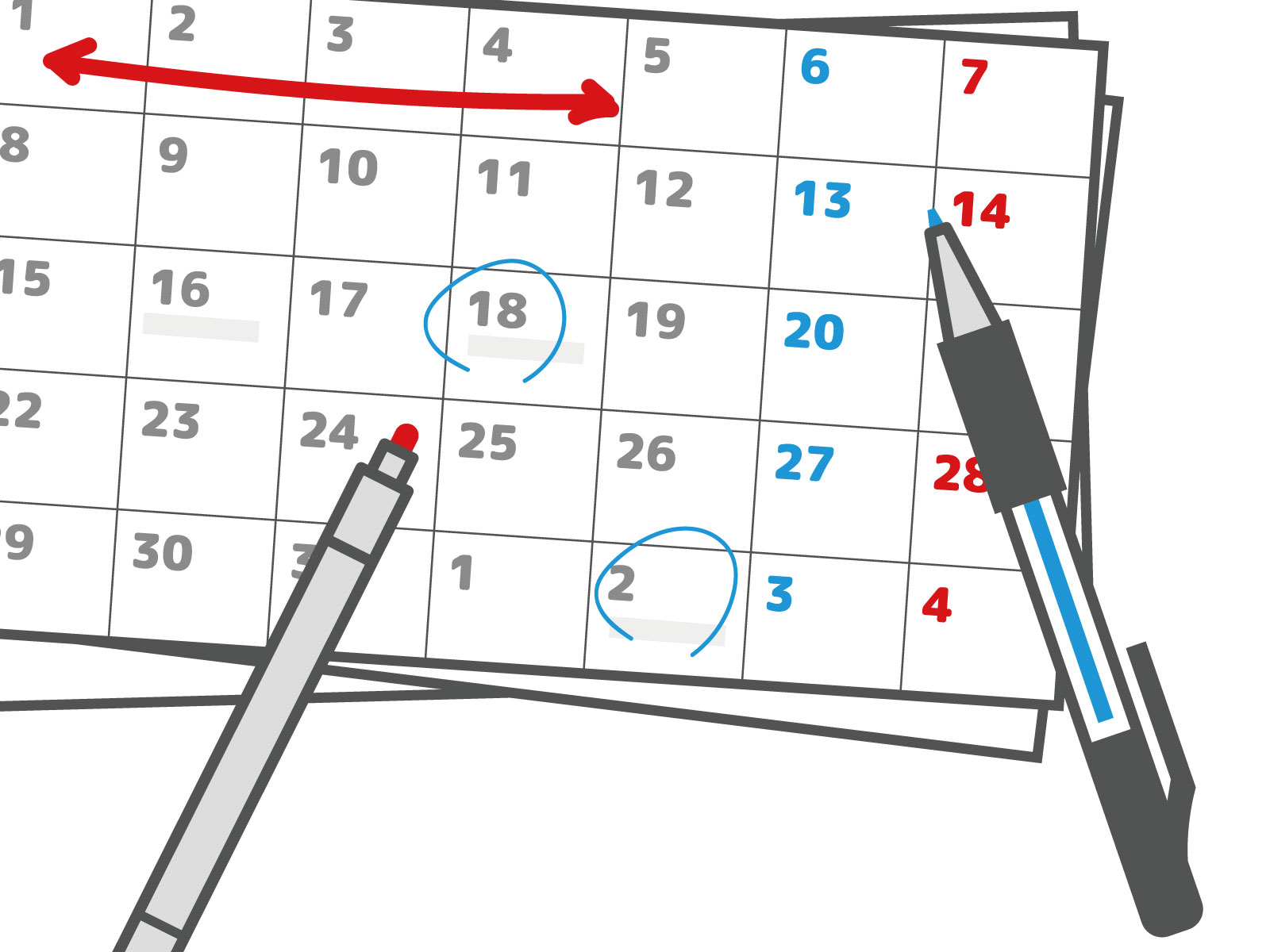
≪最適な接種時期≫
インフルエンザワクチンは、流行シーズンの前に接種することが重要です。
日本では例年12月末から翌年3月頃にかけて流行するため、1回接種の場合は遅くとも12月中旬までに接種を完了するのが望ましいです。なお、2回接種が必要な場合は、より早い時期(10月~11月中)に1回目を開始することをお勧めします。
ワクチンを接種してから効果が現れるまでには約2週間かかります。また、ワクチンの効果持続期間は約5か月とされているため、流行期間全体をカバーするためにも適切な時期の接種が大切です。
≪毎年接種が必要な理由≫
「去年打ったから今年は大丈夫」と思われる方もいらっしゃいますが、これは正しくありません。
インフルエンザウイルスは毎年少しずつ変化するため、昨年のワクチンでは今年のウイルスに対応できない可能性があります。
また、ワクチンによる免疫は時間とともに弱くなっていきます。そのため、毎年新しいワクチンを接種することが推奨されているのです。
≪接種量と回数の詳細≫
年齢によって接種量と回数が決められています。
生後6か月以上3歳未満のお子さんは、1回0.25mlを2回接種します。小さなお子さんでも安全に接種できる量に調整されています。
3歳以上13歳未満のお子さんは、1回0.5mlを2回接種します。1回目の接種から2~4週間後に2回目を接種することで、十分な免疫を獲得できます。
13歳以上の方は、1回0.5mlを1回接種するのが標準的です。
≪他のワクチンとの同時接種≫
現在では、インフルエンザワクチンと他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。新型コロナウイルスワクチンとの同時接種も可能です。
同時接種を行う場合は、接種部位を分けて行います(例:右腕にインフルエンザワクチン、左腕に新型コロナワクチン)。これにより、どちらのワクチンでも副作用が起きた場合の判別も容易になります。
≪ウイルス性疾患罹患後の接種について≫
他の病気にかかった後のワクチン接種については、病気の重さによって待機期間が決められています。
麻疹や重症感染症の場合は、治癒後4週間経ってからの接種が推奨されます。これは免疫システムが完全に回復するまでに時間がかかるためです。
中等症の場合は治癒後2週間、軽症の場合は治癒して体力が回復していれば接種可能です。
特にインフルエンザに関しては、A型・B型など異なる型のウイルスが存在するため、一度インフルエンザにかかっても別の型に感染する可能性があります。そのため、インフルエンザ罹患後であっても、治癒後1~2週間経てば接種を受けることができます。
その他の定期予防接種(肺炎球菌ワクチンなど)との同時接種も可能ですが、複数のワクチンを同時に接種する場合は、事前に医師と相談することをお勧めします。
【まとめ】
インフルエンザワクチンは、感染予防と重症化予防の両方に効果があります。副作用のリスクは低く、多くの方にとってメリットの方が大きいといえます。
特に高齢者の方、妊婦の方、慢性疾患をお持ちの方、医療従事者、小さなお子さんと接する機会の多い方は、積極的な接種をお勧めします。
毎年10月から12月上旬までの接種を心がけ、家族みんなでインフルエンザから身を守りましょう。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

