- 2025年8月16日
- 2025年9月27日
イライラ・集中力なし…その疲れ、睡眠が浅いせいかも?SASの見つけ方

「最近、些細なことでイライラしてしまう」「仕事に集中できない」「何をしても疲れが取れない」
このような症状に悩まされている方は多いのではないでしょうか。ストレス社会と言われる現代では「仕方のないこと」と思いがちです。
しかし、その原因が実は「睡眠の質の悪さ」にあるかもしれません。特に「SAS(睡眠時無呼吸症候群)」による睡眠の浅さが、日中の精神的な不調を引き起こしている可能性があります。
SASは、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。「いびき」や「日中の眠気」が代表的な症状として知られていますが、実は精神面への影響も非常に大きいのです。
「十分寝ているはずなのに疲れが取れない」「以前より怒りっぽくなった気がする」このような変化があなたにも思い当たるなら、睡眠の質を見直してみる必要があります。
今回は、睡眠の浅さがもたらす精神的な症状と、SASの見つけ方について詳しく解説します。
あなたの不調の本当の原因を探り、心身ともに健康な生活を取り戻すお手伝いをします。

この記事を書いた、院長の高見 友也です。
『不安を安心に』変えることのできるクリニックを目指して、幅広い診療を行っています。ここでは、いくつかの専門医をもつ立場から、病気のことや治療のことをわかりやすく説明しています。
プロフィールはこちらから
🎥 この記事の内容を動画でご覧いただけます
お忙しい方や、まずはざっくり知りたい方のために、この記事のポイントを動画にまとめました。ぜひご覧ください。
ラジオ風の音声形式なので、家事や移動中など「ながら聞き」にもぴったりです。
目次
【なぜ睡眠が浅いとイライラする?脳と心の深い関係】

睡眠の質が悪いと、なぜイライラしたり集中力が低下したりするのでしょうか。
その仕組みを脳科学の視点から見ていきましょう。
睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの段階があります。ノンレム睡眠の中でも特に深い段階(徐波睡眠)は、脳の疲労回復と記憶の整理に重要な役割を果たします。
SASがあると、無呼吸のたびに脳が覚醒反応を起こし、この深い睡眠が細切れになってしまいます。その結果、脳が十分に休息できず、翌日まで疲労が持ち越されます。
特に、感情をコントロールする「前頭前野」という脳の領域は、睡眠不足の影響を強く受けます。この部分が疲労すると、些細なことでイライラしたり、感情的になりやすくなります。
また、睡眠中に分泌される「セロトニン」という神経伝達物質も重要です。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させる働きがあります。睡眠の質が悪いとセロトニンの分泌が減少し、憂鬱な気分やイライラが生じやすくなります。
集中力に関わる「ドーパミン」という物質も、睡眠不足により減少します。ドーパミンは意欲や集中力を高める働きがあるため、不足すると「やる気が出ない」「集中できない」という状態になります。
さらに、慢性的な酸素不足により、脳の神経細胞が軽度の障害を受けることもあります。これにより、判断力や思考力が低下し、普段なら簡単にできることができなくなってしまいます。
ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌パターンも乱れます。通常は朝に高く夜に低くなるのですが、SASがあると一日中高い状態が続き、慢性的なストレス状態になります。
これらの複数の要因が重なることで、「イライラしやすい」「集中できない」「疲れが取れない」という症状が現れるのです。
【あなたは大丈夫?SASによる精神症状セルフチェック】

SASによる精神的な影響は多岐にわたります。以下の項目をチェックして、あなたの症状と照らし合わせてみてください。
感情面の変化として、些細なことでイライラするようになった、家族や同僚に対して怒りっぽくなった、以前なら気にならないことが気になるようになったという症状があります。
また、気分が沈みがちになる、楽しいと感じることが減った、何に対してもやる気が起きないという抑うつ的な症状も現れることがあります。
集中力に関しては、仕事や勉強に集中できない、読書やテレビを見ていても内容が頭に入らない、会議や授業中に別のことを考えてしまうといった症状が見られます。
記憶力の低下も深刻な問題です。人の名前が出てこない、約束を忘れやすくなった、新しいことを覚えるのに時間がかかるようになったという変化があります。
判断力や決断力の低下も特徴的です。普段なら簡単に決められることに時間がかかる、優先順位をつけるのが困難になる、ミスが増えるといった症状が現れます。
社交面では、人と会うのが億劫になった、コミュニケーションを取るのが疲れる、家族との会話が減ったという変化が見られることがあります。
身体的な症状も精神状態に影響します。朝起きたときから疲れている、一日中だるさが続く、頭が重い感じがするといった症状があります。
食欲の変化も重要なサインです。食欲がない、または逆に過食気味になる、特に夜間に食べ過ぎてしまうという症状が現れることがあります。
睡眠に関しては、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めてしまう、悪夢を見ることが増えたという症状があります。
これらの症状が複数当てはまる場合は、SASの可能性を疑って医療機関を受診することをお勧めします。
【早期発見が鍵!SASを見つける方法と治療への第一歩】
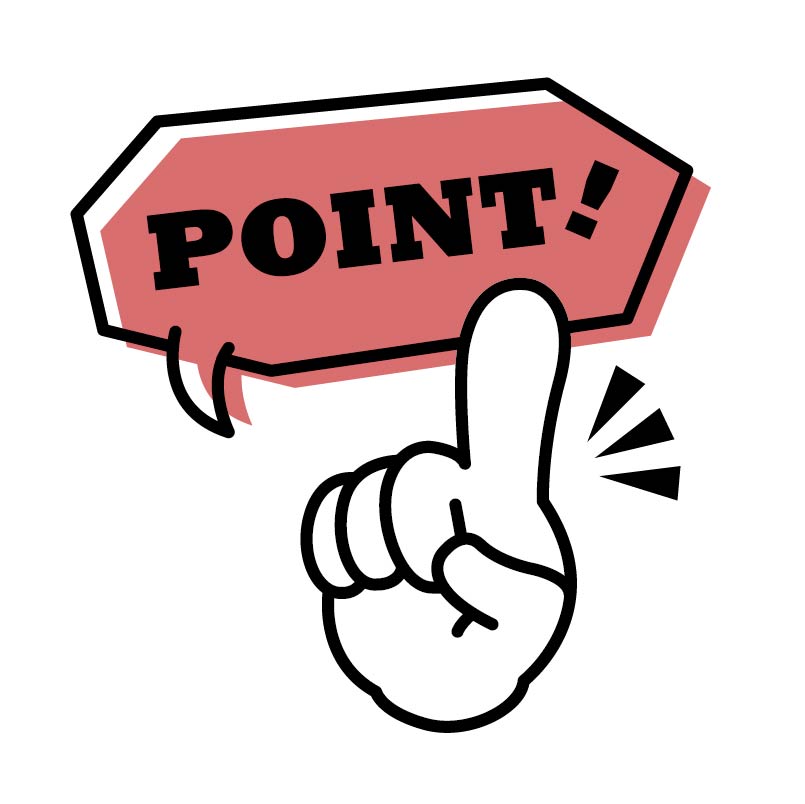
SASの早期発見は、精神的な症状の改善だけでなく、将来の重大な合併症を防ぐためにも重要です。では、どのようにSASを見つければよいのでしょうか。
まず、家族やパートナーからの情報が非常に重要です。「いびきがひどい」「息が止まっている時がある」「苦しそうに寝ている」という指摘があれば、SASの可能性が高いです。
自分自身で気づくサインとしては、朝起きたときの口の渇き、頭痛、のどの痛みなどがあります。また、日中の強い眠気、特に静かな環境での居眠りも重要なサインです。
最近では、スマートフォンのアプリやウェアラブル端末を使って、睡眠の質をチェックできるものもあります。いびきの記録や睡眠の深さを測定できるため、参考になります。
医療機関での検査方法もご紹介します。
まず、問診票や睡眠日誌により、症状や睡眠パターンを詳しく調べます。エプワース眠気尺度という標準化された質問票で、日中の眠気の程度を評価します。
簡易検査として、自宅でできる携帯用の機器を使った検査があります。指に酸素濃度を測る機器をつけ、鼻に呼吸センサーをつけて一晩眠るだけで、呼吸の状態を調べることができます。
検査については、睡眠時無呼吸は簡単な検査でわかります|自宅でできる検査とは?もご参照ください。
より詳しい検査が必要な場合は、病院で一泊する「終夜睡眠ポリグラフ検査」を行います。これは最も正確な検査で、脳波、呼吸、心電図、筋電図などを同時に記録し、睡眠の状態を詳細に分析します。
治療方法も大きく進歩しています。軽症の場合は、生活習慣の改善(減量、禁煙、節酒、横向き寝など)で症状が改善することがあります。
中等症から重症の場合は、CPAP療法(シーパップ療法)が第一選択となります。これは、睡眠中に専用のマスクから空気を送り込み、気道を開いた状態に保つ治療法です。
マウスピース療法や手術療法も、患者さんの状態に応じて選択されます。最近では、舌下神経刺激療法という新しい治療法も登場しています。
治療については、マウスピース?CPAP?治療法の違いと選び方を解説しますもご参照ください。
心当たりのある方は、是非お気軽にご相談ください。
なお検査から治療に関しては、こちら睡眠時無呼吸の検査はどこで受けられる?流れを丁寧にご紹介もご参照ください。
まとめ
イライラ、集中力低下、疲労感といった症状は、単なるストレスや性格の問題ではなく、睡眠の質の悪さが原因かもしれません。特にSASによる睡眠の浅さは、脳の機能に深刻な影響を与え、日常生活の質を大きく低下させます。
しかし、適切な診断と治療により、これらの症状は大幅に改善できます。CPAP療法を始めた多くの患者さんが、「性格が明るくなった」「仕事の効率が上がった」「家族関係が良くなった」と報告されています。
精神的な不調を感じている方は、まず睡眠の質を見直してみてください。パートナーからいびきを指摘されたことがある、朝起きたときに疲れが残っている、日中に強い眠気を感じるといった症状があれば、お気軽にご相談ください。
「最近の不調は年のせい」「ストレスが原因」と諦める前に、睡眠という基本的な生活習慣に目を向けてみましょう。質の良い睡眠を取り戻すことで、心も体も健康で充実した毎日を送れるようになります。
あなたの症状改善への第一歩は、正しい知識を持ち、適切な医療機関を受診することから始まります。一人で悩まず、専門医と一緒に解決策を見つけていきましょう。

